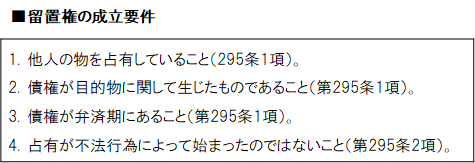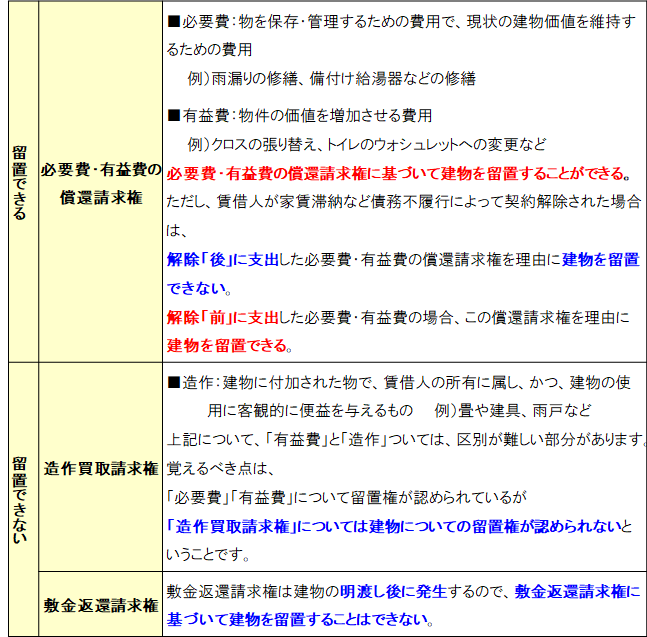改正民法に対応済
留置権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- Aは自己所有の建物をBに売却し登記をBに移転した上で、建物の引渡しは代金と引換えにすることを約していたが、Bが代金を支払わないうちにCに当該建物を転売し移転登記を済ませてしまった場合、Aは、Cからの建物引渡請求に対して、Bに対する代金債権を保全するために留置権を行使することができる。
- Aが自己所有の建物をBに売却し引き渡したが、登記をBに移転する前にCに二重に売却しCが先に登記を備えた場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することができる。
- AがC所有の建物をBに売却し引き渡したが、Cから所有権を取得して移転することができなかった場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできない。
- Aが自己所有の建物をBに賃貸したが、Bの賃料不払いがあったため賃貸借契約を解除したところ、その後も建物の占有をBが続け、有益費を支出したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、Aに対する有益費償還請求権を保全するために留置権を行使することはできない。
- Aが自己所有の建物をBに賃貸しBからAへ敷金が交付された場合において、賃貸借契約が終了したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、Aに対する敷金返還請求権を保全するために、同時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできない。
【解説】
1・・・妥当
他人物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができます(民法295条)。
※ 留置権の成立要件は下表参照
■本問を見ると、建物は、AからB、BからCと売却されているので、「所有権」はCに移っています。しかし、Aはまだ、代金をもらっていないので建物の引き渡しをしていない状況です。つまり、「他人物の占有者=A」です。そして、代金債権は「建物に関して生じた債権」です(上表の成立要件の2参照)。よって、Aは、295条の留置権を持ちます。
留置権は、物権なので、「代金債権の債務者B」だけでなく、Cに対しても主張できます。つまり、Aは、Cから建物引渡請求に対して、「代金を支払ってもらうまで、建物は引渡しません!」と留置権を行使できます。
2・・・妥当ではない
判例によると、不動産の二重譲渡において、「登記を得られなかった者Bが取得した損害賠償請求債権」を担保するために、留置権を行使することはできないとしています。
【理由】 Bの有する損害賠償請求権は、成立要件の2の「目的物(建物)に関して生じた債権」ではありません。Aの債務不履行(履行不能)によって生じた債権です。選択肢1の代金債権は、「建物」が「代金」に価値を替えたもので、
損害賠償請求とは違います。そのため、当該損害賠償請求権では、留置権は成立せず(Bは留置権を行使できない) 、BはCからの明渡請求を拒むことができません。
3・・・妥当
判例によると、他人物売買の買主Bは、所有者Cの目的物の返還請求に対し、所有権を移転するはずであった売主Aの債務不履行による損害賠償債権のために、留置権を主張できないとしています。
【理由】 考え方は選択肢2と同じです。Bの有する損害賠償請求権は、
成立要件の2の「目的物(建物)に関して生じた債権」ではありません。
Aの債務不履行によって生じた債権です。
そのため、留置権は成立せず(Bは留置権を行使できない)、BはCからの明渡請求を拒むことができません。
4・・・妥当
ただし、賃料不払いによる契約解除後に支出した必要費・有益費の場合、償還請求権に基づいて留置できない
「有益費」とは、物件の価値を増加させる費用を指し、例えば、トイレのウォシュレットへの変更に要した費用です。
そして、契約解除前に、賃借人Bが有益費を支払ったにもかかわらず、賃貸人Aが有益費を支払ってくれない場合、賃借人Bは、賃貸借契約が終了しても、留置権に基づいて、建物の明渡しを拒むことができます。つまり、賃借人Bが有益費を支出した場合は、その償還(弁済)を受けるまで留置権により、建物の返還を拒否できます。(ただし、その際、契約終了後の賃料相当額は賃貸人Aに支払う必要はあります。)
一方、賃料不払いを理由に契約解除となった後に支出した有益費については、留置権は成立せず、建物の明け渡しを拒むことはできません(判例)。
【理由】 賃料不払いを理由として契約解除となった後は、 建物の占有が不法行為によって始まったことになります。
つまり、選択肢1の「留置権の成立要件の4」を満たさないので、留置権は成立しない。
※ 必要費とは、建物を保存する費用のことで、例えば、雨漏りの修理費用などです。
5・・・妥当
賃借人の建物明渡債務の履行が先 → その後に、賃貸人は敷金を返還すればよい
【判例と理由】 判例によると、「賃借人の建物の明渡し」と「賃貸人の敷金返還」は、 「賃借人の建物の明渡し」が先で、その後に「賃貸人は敷金を返還すればよい」としています。つまり、「建物明渡債務」と「敷金返還債務」とは、同時履行の関係にありません。上記理由から、賃借人Bは、留置権を行使することはできません。
【別の考え方】
また、上記に付随した考え方として、敷金返還請求権は、建物の明渡し後に発生するものなので、明渡し前は、敷金返還請求権は発生していないので、敷金返還請求権に基づいて建物を留置することはできない。
平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説
| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
| 問3 | 外国人の人権 | 問33 | 民法:債権 |
| 問4 | 基本的人権 | 問34 | 民法:債権 |
| 問5 | 憲法9条 | 問35 | 民法:親族 |
| 問6 | 司法の限界 | 問36 | 商法 |
| 問7 | 財政 | 問37 | 会社法 |
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
| 問10 | 行政立法 | 問40 | 会社法 |
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
| 問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 一般知識・政治 |
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 一般知識・政治 |
| 問19 | 国家賠償法 | 問49 | 一般知識・社会 |
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 一般知識・経済 |
| 問21 | 地方自治法 | 問51 | 一般知識・社会 |
| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 一般知識・社会 |
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 一般知識・社会 |
| 問24 | 行政法 | 問54 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問25 | 行政法 | 問55 | 一般知識・情報通信 |
| 問26 | 行政法 | 問56 | 一般知識・個人情報保護 |
| 問27 | 民法:総則 | 問57 | 一般知識・情報通信 |
| 問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
| 問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
| 問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |